2025-10-22
社会保険労務士 齊藤労務事務所 齊藤 拓也
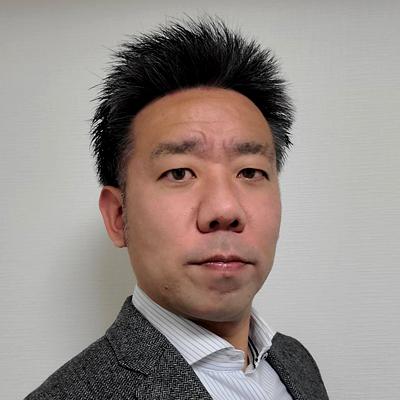
ふるさと納税の恩恵を受けることができる給与水準
人事・労務
皆様、こんにちは。
社会保険労務士の齊藤です。
年末が近づいてきましたが、年間の収入額、所得額が概ね把握できるようになるタイミングですので、この時期はふるさと納税の準備をし始める方が多いのではないでしょうか。実際、筆者の周囲でもふるさと納税の話題が多くなってくる季節ではあります。今年はポイント付与の廃止もありましたので、例年よりもふるさと納税について見聞きする機会が多い印象です。
さて、給与計算業務に広く関与している立場上、ふるさと納税のお問い合わせを頂くことが少なくありません。毎年のように「ふるさと納税はした方が良いか」、「自身はふるさと納税をできるのか」といったご質問を多く頂きます。このようなご質問を頂くたびに、意外にもふるさと納税や住民税の仕組みは理解されていないなと再認識します。そこで今回のコラムでは、ふるさと納税の恩恵を受けることができる給与水準について書きたいと思います。
ふるさと納税とは
過去のコラム「ふるさと納税の恩恵と寄附金上限額」でも書きましたが、ふるさと納税を簡単に説明すると次のような感じになります。
- 翌年に納めるべき住民税の前払い。
- 寄附した年の所得税が軽減される。
- 寄附した市区町村から返戻品がもらえる。
ふるさと納税は住民税の前払いという性質がありますので、住民税が課税されない人によるふるさと納税は、それこそ純粋な寄附に過ぎません。寄附することに目的があれば何ら問題はありませんが、「返礼品がもらえたのでお得」のような感覚でいると、全くそのようなことにはなっていませんので注意が必要です。ふるさと納税は、住民税を前払いするだけなのに返礼品がもらえるからお得と言われるのであって、住民税の前払いの効果がなかった場合は、単に自身の持ち出しが増えるだけになります。
住民税の壁は110万円
こちらも過去のコラム「結局「103万円の壁」はどうなった?」で触れましたが、令和7年から給与所得控除の下限が55万円から65万円に改正されたとともに、合計所得金額2,350万円以下の納税者の基礎控除が48万円から58万円以上(最大95万円)に改正されました。この2つの改正は所得税の課税に関するものですが、この改正によって給与収入160万円(給与所得控除65万円+基礎控除95万円)までは所得税がかからないことになりました。いわゆる160万円の壁です。
一方、住民税については、給与所得控除は所得税と同様65万円が適用されるものの、基礎控除は従前どおり43万円のままになっています。住民税の課税されるラインについては、所得税のように65万円+43万円=108万円と考えてしまいそうですが、そうではありません。住民税には非課税限度額が設けられており、単身者の場合の非課税限度額は45万円とされています。これも従前から変わっていません。つまり、給与所得控除65万円と非課税限度額45万円を足した給与収入110万円までは住民税はかからないことになります。これが住民税の110万円の壁を指しますが、「住民税が課税されない=ふるさと納税の恩恵はない」ことになりますので、ふるさと納税を検討するにあたっては、給与収入が110万円超であることが大前提になります。
課税所得が40万円程度を超えてくるとふるさと納税の恩恵を享受できる可能性がある
例えば、給与収入が120万円(単身の会社員で、給与所得控除、基礎控除以外の控除はなし)だった場合、自己負担2,000円で済むふるさと納税の寄附金上限額は次のとおりになります。計算方法の詳細については先述の過去コラム「ふるさと納税の恩恵と寄附金上限額」をご参照ください。
- 住民税所得割額:(120万円-給与所得控除65万円-基礎控除43万円)×10%=12,000円
- 寄附金上限額:12,000円×20%÷90%+2,000円≒4,666円 → 4,000円
上記のように、給与収入120万円(課税所得12万円)時には、自己負担2,000円の範囲内で4,000円を寄附することができますが、ふるさと納税を寄附する場合は、返礼品を目当てにするケースが多いと思われます。制度上、返礼品は寄附額の3割以下とされている中、必ず自己負担2,000円が生じることを考慮しますと、2,000円以上の返礼品を受けて初めてふるさと納税で得をしたと捉えることができますので、逆算すると2,000円の返礼品をもらうためには7,000円程度の寄附が必要になってきます。
住民税所得割額が25,000円(課税所得25万円)程度の時に寄附金上限額が7,000円になりますが、ふるさと納税を仲介する各社のサイトを見ていますと、寄付額10,000円辺りから返礼品が充実してくる印象があります。住民税所得割額が40,000円(課税所得40万円)程度の時の寄附金上限額が10,000円です。返礼品にある程度の価値がないと多くの寄附を募ることはできないでしょうから、寄附額の最低ラインが10,000円程度に落ち着くのは合点がいきます。
以上を総合しますと、課税所得が12万円程度では返礼品によるお得感を享受することは期待できませんが、課税所得が25万円程度を上回ってくると、自己負担2,000円以上の経済的なメリットを受けることが可能になってくると言えます。そして、相応の返礼品をもらうことを想定した場合、概ね課税所得が40万円前後を超えてきた時に寄附の選択肢が増えて、実際に寄附ができる状況になると考えられます。従いまして、考え方は人それぞれではありますが、返礼品の恩恵や確定申告の労力等も踏まえますと、課税所得が40万円程度以上の場合には、ふるさと納税による寄附を前向きに検討した方が良いと言えるのではないでしょうか。
なお、課税所得は、給与収入から給与所得控除と基礎控除のほか、社会保険料等を控除して算出します。単身の会社員の場合は、概ね給与収入170万円程度が課税所得40万円の目安になってきますので、自身の給与収入が170万円程度以上見込まれる時は、ふるさと納税を仲介する各社のサイト等でふるさと納税の可能額をシミュレーションしてみると良いかもしれません。
今回はふるさと納税に関するコラムでした。
これからも、本コラムを通じて皆様へ有益な情報をお届けできればと思います。
このコラムを書いたのは
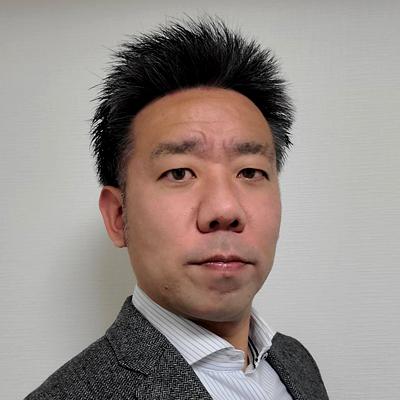
社会保険労務士 齊藤労務事務所 齊藤 拓也
千葉県市原市生まれの墨田区在住。
地方銀行(千葉県)、金融商品デリバティブ取引所、ファイナンシャルプランナーの団体、社会保険労務士法人でのキャリアを経て2020年4月、東京都中央区日本橋に「齊藤労務事務所」を開業。就業規則整備、助成金活用の提案をメイン業務として活動中。
現在は第一線から退いているもののパチンコ業界にはユーザとして長く関与。大学生活では文武両道に努めつつ「オークス2」、「セブンショック」、「CRモンスターハウス」、「CR必殺仕事人」に熱中。大学卒業後はスロットへ路線変更して「花伝説」、「猛獣王」、「アントニオ猪木という名のパチスロ機」、「スーパービンゴ」、「北斗の拳」などで万枚の大台を記録。好きな機種は「ハナハナ」。
地方銀行(千葉県)、金融商品デリバティブ取引所、ファイナンシャルプランナーの団体、社会保険労務士法人でのキャリアを経て2020年4月、東京都中央区日本橋に「齊藤労務事務所」を開業。就業規則整備、助成金活用の提案をメイン業務として活動中。
現在は第一線から退いているもののパチンコ業界にはユーザとして長く関与。大学生活では文武両道に努めつつ「オークス2」、「セブンショック」、「CRモンスターハウス」、「CR必殺仕事人」に熱中。大学卒業後はスロットへ路線変更して「花伝説」、「猛獣王」、「アントニオ猪木という名のパチスロ機」、「スーパービンゴ」、「北斗の拳」などで万枚の大台を記録。好きな機種は「ハナハナ」。
