2024-10-23
社会保険労務士 齊藤労務事務所 齊藤 拓也
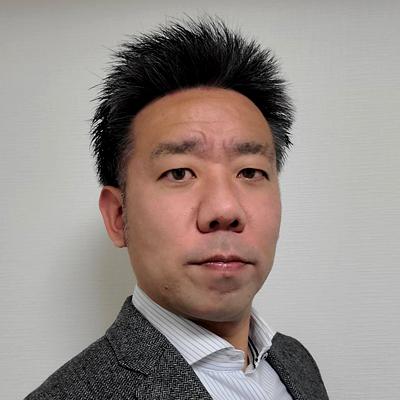
令和6年分年末調整の主な留意点
人事・労務
皆様、こんにちは。
社会保険労務士の齊藤です。
今回は「令和6年分年末調整の主な留意点」に関するコラムになります。
そもそも年末調整とは、1年間の所得税を精算することを指します。
所得税は、給与と賞与でそれっぽい額が天引きされていますが、源泉徴収税額表に基づいて天引きされてはいるものの暫定的に天引きされているに過ぎません。その年に納付すべき所得税額は、最終的に年間の所得額で決まります。その納付すべき所得税額を確認する作業が年末調整であり、ざっくり次のようなフローで行われます。
- ①給与と賞与で天引きした所得税を集計
- ②所得額に応じた所得税を計算
- ③②と①の差額を「還付(①>②の場合)」又は「徴収(①<②の場合)」
結局、納めるべき所得税額は②で決まりますので、極端に言うと、給与と賞与で天引きされる所得税が何円であっても所得税額に影響はありません。例えば、②で計算した額が10万円だった場合、①での天引き額が20万円でも0円でも、③の処理により、いずれも年間の持ち出しが10万円になることはお分かりいただけるかと思います。
定額減税の月次減税の有無とその損得についてお問い合わせを頂くことが少なくありませんが、上記年末調整の仕組みを把握しておけば、月次減税の有無に損得はない、月次減税の有無が所得税の計算に何ら影響を及ぼすことはないことがご理解いただけるかと思います。月次減税は、暫定的に天引きされている所得税を暫定的に少なくしているだけ(とりあえず手取りを多く見せているだけ)なのです。
さて、それでは令和6年分年末調整の主な留意点について3点説明いたします。
同一生計配偶者と扶養親族を改めて確認
令和6年6月からの月次減税の処理にあたっては、同一生計配偶者と扶養親族の人数、所得等を確認したと思いますが、令和6年分の年末調整では、改めてその状況を確認する必要があります。なぜならば、最終的に年末時点の同一生計配偶者と扶養親族の状況で年調減税(2つ目の留意点で説明)を行う必要があるからです。
ちなみに、月次減税対象の社員の場合、令和6年6月2日以降に同一生計配偶者又は扶養親族の人数に異動があった時は、月次減税額と年調減税額が異なることになります。例えば、令和6年6月1日時点では月次減税額60,000円(自身と同一生計配偶者)だったものの、その後、配偶者の出産により扶養親族として子が一人追加されて年調減税額が90,000円(自身と同一生計配偶者と子)になるような場合です。
反対に、離婚等の場合は、月次減税額が120,000円だったのに年調減税額が30,000円になるようなことが起こり得ます。なお、このような「月次減税額>年調減税額」になった時は、結果的に給与と賞与で天引きした所得税が少なかったこと(所得税を30,000円しか控除できなかったのに120,000円も控除していたこと)になるため、年末調整で不足分の所得税を徴収される可能性があります。
年調減税の処理がある
例年の年末調整と異なり、令和6年分の年末調整では年調減税の処理が入ります。
下記が令和6年の年末調整の精算イメージになります。イメージしやすいよう税額、減税額等を例示していますが、あくまで説明のための便宜的な数字であり、所得額や税率は一切考慮していません。また、復興特別所得税の計算は省略しています。
- ①給与及び賞与で天引きされた所得税(月次減税処理後の所得税)を集計 例150,000円
- ②確定した所得額で所得税(=年調所得税額。以降同じ)を計算 例140,000円
- ③年調減税額の確認 例30,000円
- ④年調減税を反映した所得税(②-③)を計算 例110,000円
- ⑤①と④の差額を還付又は徴収 例40,000円還付
月次減税は6月以降の給与及び賞与での処理でしたが、年末調整では年調減税という形で定額減税を反映させます(③、④)。感覚的に6月以降の給与及び賞与で減税されていたと認識しがちですが、年調減税こそが本来の減税に当たります。「月次減税は手取りを増やすためだけのもので所得税の計算には一切関係のない処理」、「年調減税は税額を計算するための処理」という認識で差し支えないです。
源泉徴収票への記載
令和6年中の退職に伴う源泉徴収票には定額減税の情報を記載する必要はありませんが、年末調整済みの源泉徴収票には、その摘要欄に定額減税の情報を記載する必要があります。
具体的には、「実際に控除した年調減税額」を記載することとなります。例えば、年調減税額が30,000円でそれを全額控除した場合は、「源泉徴収時所得税減税控除済額30,000円 控除外額0円」と記載します。
一方、年調所得税額が年調減税額を下回った場合は、年調所得税額、つまり、「実際に控除した年調減税額」を記載することとなり、加えて、控除できなかった分を控除外額として記載します。例えば、年調所得税額20,000円、年調減税額30,000円だった場合は、「源泉徴収時所得税減税控除済額20,000円 控除外額10,000円」と記載します。
上記の他、合計所得金額が1,000万円超である社員の同一生計配偶者(非控除対象配偶者)分を年調減税額の計算に含めた場合は、同じく摘要欄に「非控除対象配偶者減税有」と記載する必要があります。
今回は、「令和6年分年末調整の主な留意点」について書かせていただきました。
「年調減税の処理」や「源泉徴収票の記載」は、給与システムでカバーできる部分ですので、対応漏れ等は考えにくいと思いますが、「同一生計配偶者と扶養親族を改めて確認」に関しては、「異動があったのに月次減税対応時の情報を引き継いで処理してしまった」、「配偶者特別控除の対象である配偶者を同一生計配偶者として処理してしまった」等の誤りが懸念されます。令和6年分の年末調整を行うにあたっては、今一度、国税庁のホームページ等で作業方法を確認して、事務ミスを起こさないようご注意下さい。
これからも、本コラムを通じて皆様へ有益な情報をお届けできればと思います。
このコラムを書いたのは
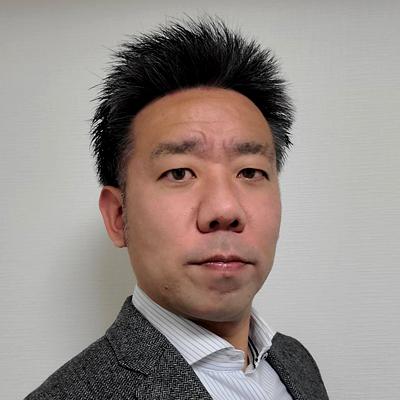
社会保険労務士 齊藤労務事務所 齊藤 拓也
千葉県市原市生まれの墨田区在住。
地方銀行(千葉県)、金融商品デリバティブ取引所、ファイナンシャルプランナーの団体、社会保険労務士法人でのキャリアを経て2020年4月、東京都中央区日本橋に「齊藤労務事務所」を開業。就業規則整備、助成金活用の提案をメイン業務として活動中。
現在は第一線から退いているもののパチンコ業界にはユーザとして長く関与。大学生活では文武両道に努めつつ「オークス2」、「セブンショック」、「CRモンスターハウス」、「CR必殺仕事人」に熱中。大学卒業後はスロットへ路線変更して「花伝説」、「猛獣王」、「アントニオ猪木という名のパチスロ機」、「スーパービンゴ」、「北斗の拳」などで万枚の大台を記録。好きな機種は「ハナハナ」。
地方銀行(千葉県)、金融商品デリバティブ取引所、ファイナンシャルプランナーの団体、社会保険労務士法人でのキャリアを経て2020年4月、東京都中央区日本橋に「齊藤労務事務所」を開業。就業規則整備、助成金活用の提案をメイン業務として活動中。
現在は第一線から退いているもののパチンコ業界にはユーザとして長く関与。大学生活では文武両道に努めつつ「オークス2」、「セブンショック」、「CRモンスターハウス」、「CR必殺仕事人」に熱中。大学卒業後はスロットへ路線変更して「花伝説」、「猛獣王」、「アントニオ猪木という名のパチスロ機」、「スーパービンゴ」、「北斗の拳」などで万枚の大台を記録。好きな機種は「ハナハナ」。
