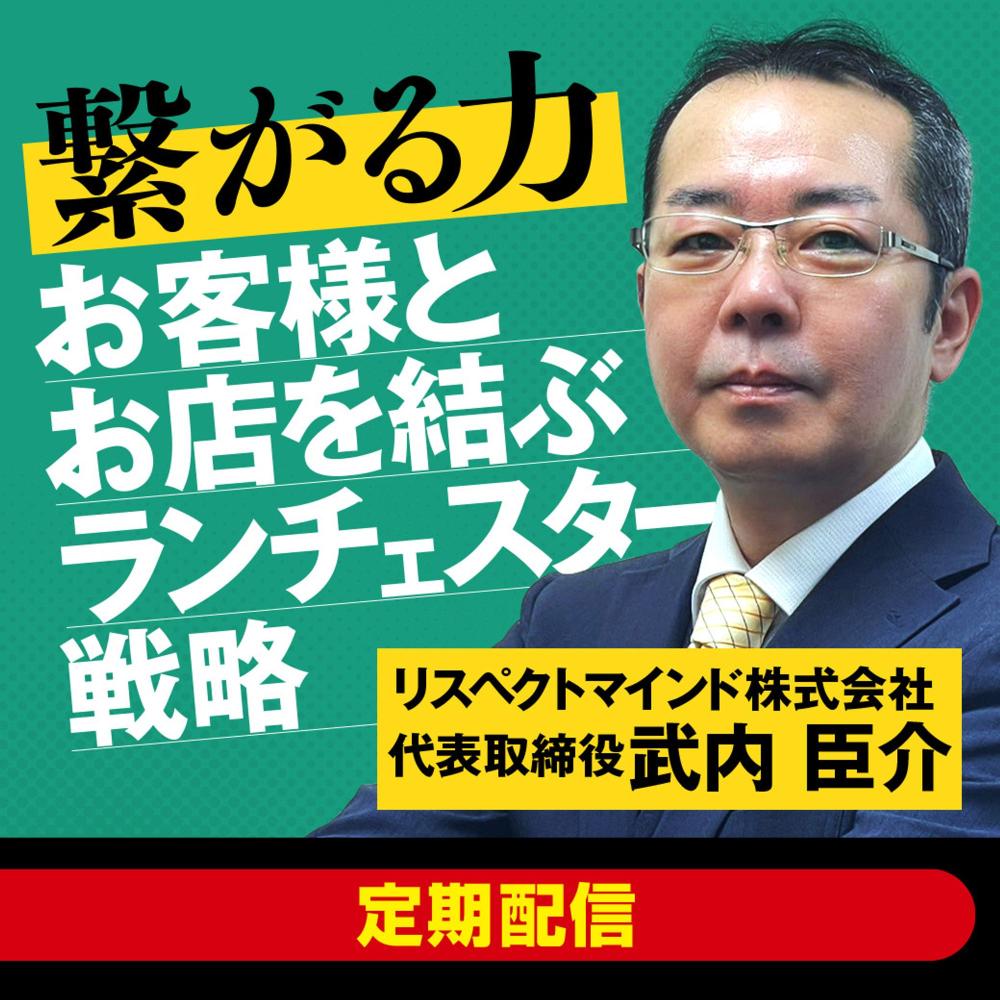2025-03-26
リスペクトマインド株式会社 代表取締役 武内 臣介

繋がる力 お客様とお店を結ぶランチェスター戦略「増客に欠かせない両輪!!『市場浸透戦略』と『市場開拓戦略』」
業界情報
こんにちは!リスペクトマインド(株)の武内臣介です。
前回コラムでは、≪デカへその可能性≫について書きました。
また、2024年11月からのコラムでは、年末年始の営業実績から自店のボトルネックを探して、4月に市場へ転入する方々やゴールデンウィークでの集客を目指した取組みとして改善するという内容も書いてきました。
4月の重要な時期は目前なので、このタイミングでは自店商圏と自店の顧客を減らさないための営業施策を更に充実させることが大切です。
そこで、営業施策を充実させるための土台となる考え方として、『市場浸透戦略』と『市場開拓戦略』について書いていきます。
アンゾフの成長マトリクス
事業を成長させるために考えるフレームワークとして、古典的なものに『アンゾフの成長マトリクス』があり、発表から67年ほど経過していますが現在でも活用できる考え方です。
これは4つの成長戦略を考えるものになります。
- ①既存市場×既存製品(市場浸透戦略)
- ②既存市場×新製品 (製品開発戦略)
- ③新市場×既存製品(市場開拓戦略)
- ④新市場×新製品(多角化戦略)
各詳細説明は省きますが、パチンコ業界で通常の新台入替やプロモーションを工夫する際は、①市場浸透戦略と③市場開拓戦略の考え方が必要になります。
市場浸透戦略
[既存の市場に対して、既存の商品を浸透させていく戦略]です。
≪市場≫という言葉は普通に使われますが、既存の市場という場合は「既存のお客様、自店、他店、商品群」という商売を構成している範囲を言います。
細かく構成要素を見ていくと、市場を構成しているお客様の職業や所得、男女比や年齢割合から、自店、他店が提供している商品群となる機種構成などなど、商売が成立している要素に関するものです。
パチンコやスロットを遊技してもらう商売ですが、お客様に何かしらの機種とつながってもらうことで、稼働や売上を形成していきます。
そこで、『市場浸透戦略』を考える場合は、既存の商品ではあるが、それを既存のお客様の中でもその商品を知らない人に浸透させていき、対象商品の利用者を増やしていくという戦略になります。
機種単体の浸透の場合、機種ファンの分母を増やすことが浸透戦略となり、カテゴリーの浸透の場合は、スマパチやスマスロ、機種タイプ、ラッキートリガー、デカへそ・・・など、それぞれの価値を訴求して、各カテゴリーのお客様という分母を増やすことが浸透戦略になります。
前回コラムで書いた『デカへその可能性』というのは、今後リリースされる新台を活用して価値認知を高め、知らない人がレパートリーの一つにすることで『デカへそ』の認知が広がり、遊技するファンが増えることで分母も増えていくという浸透戦略になります。
これはデカへそ機種に限ったことではなく、ファンを増やす(分母を増やす)というのは、パチンコとスロットのカテゴリーから始まり、確率別、タイプ別、機種別に考えて、より効果が高い商品を浸透させていくものになります。
市場開拓戦略
[新市場に対して、既存の商品を活用してお客様を増やしていく戦略]です。
基本的な考え方は、ある商品がどこかの市場で成功した場合、その商品で新しい市場に参入して開拓するものです。
競合他社も参入していない市場や、既存の商品を海外に展開するときに活用する戦略ですが、パチンコ業界としては更に応用した考え方が有効になります。
市場開拓とは、いわゆる新規顧客開拓になります。
自店商圏は変わらなくても、毎年4月には遊技が出来る年齢に達する方や、他の市場から転勤などで市場に流入する方もいます。
他の市場でパチンコやスロットのユーザーだった場合は、市場浸透戦略の考え方で自店を選んでもらうアプローチになりますが、自店商圏の新規ユーザー開拓を行う場合は市場開拓戦略の考え方で施策を考える必要があります。
市場開拓戦略は、『未経験の方や休眠ユーザーの方に来店してもらうためのアプローチ』から考えるものになります。
「未経験の方に来店してもらうのは難しいし効率が悪い」と一刀両断してしまえば市場は先細りしていくだけです。
未経験といってもパチンコやスロットに対する温度感は異なり、「行ける歳になったら行ってみたい」「興味はあるので誰かが一緒に行ってくれたら行きたい」「まったく興味が無い」などなど、可能性としては様々ですが、興味関心を高めるアプローチから、自店の機種とつながってもらうための営業施策までの流れを考えるものになります。
市場開拓戦略が実施しやすいタイミングとしては、話題性がある商品やカテゴリーで価値提案しやすいときになります。
4月が特に重要ですが、基本的には1年を通して有効なタイミングを活用するものになります。
市場時期別のアプローチ
市場浸透戦略も市場開拓戦略も、どちらも『市場時期別』の取組みを考えて変化させていく必要があります。
『市場時期別』の取組みを考える際には、イノベーター理論とプロダクトライフサイクル曲線の考え方も取り入れます。
イノベーター理論は、お客様の商品購入に対する態度で、積極的な方もいれば受動的な方も存在し、5つのタイプによってアプローチを変える必要があるというものです。
プロダクトライフサイクル曲線は、市場に商品が浸透していくときの流れになります。
イノベーター理論とプロダクトライフル曲線の関係は下記の通りになります。
イノベーター理論とプロダクトライフサイクル曲線
- イノベーター(2.5%)革新者
- ⇒自らの判断で早い段階で行動するタイプ(積極的)
※プロダクトライフサイクル曲線での導入期になります
- アーリーアダプター(13.5%)初期採用者
- ⇒自らの判断でイノベーターに少し遅れて行動するタイプで、オピニオンリーダーとして周囲に影響を与える存在(積極的)
※プロダクトライフサイクル曲線の成長期になります
- アーリーマジョリティ(34%)前期追随者
- ⇒新しい商品に対して慎重で、アーリーアダプター(初期採用者)の評価や評判に影響を受け、良さそうであればそこから考えて行動を始めるタイプ(受動的)
※プロダクトライフサイクル曲線の成長後期になります
- レイトマジョリティ(34%)後期追随者
- ⇒新しい商品に対して懐疑的で、アーリーマジョリティに浸透して多くの人が良い評価になり、普及率が高まってから行動を始めるタイプ(受動的)
※プロダクトライフサイクル曲線の成熟期になります
- ラガード(16%)採用遅滞者
- ⇒保守的で変化を好まないタイプで、市場に商品やサービスが浸透した後、必要に迫られて商品を購入していく層(受動的)
※プロダクトライフサイクル曲線の飽和期と減衰期になります
『市場浸透戦略』と『市場開拓戦略』の課題
アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間にはキャズムという溝があります。
アーリーアダプターの評価が好ましくないとマジョリティ層に商品は浸透していきません。
これは自社の新商品を浸透させるときの重要な課題でキャズム越えをどの企業も狙って商品開発を行います。
ホールにおいては、イノベーターとアーリーアダプターが良い評価をしてくれた商品を市場浸透戦略としてマジョリティ層へ広げていくことが重要な課題です。
イノベーターとアーリーアダプターが良い評価をしてくれたポイントをマジョリティ層に対して『価値提案』して訴求していくことと、新規ユーザーに対しても良い評価の機種をレパートリーにしてもらうことでリピート率を上げる可能性が高まります。
マジョリティ層への浸透が【重要な課題】ですが、実際の営業施策でこれが出来ているかを自店でチェックする必要があります。
昨今では、大手のチェーン店でもお客様がデータ表示器の機能を自ら操作をしないと『確率・突入率・継続率』という基本的な情報から、更には機種を打ちたくなるポイントなどが分からない状態になっているところもあります。
異業種で商売をしている友人とホールに行ったとき、その友人が「商品を売る気が無いように感じる」と厳しいコメントをしていました。
キャズムを超えて受動的な方々にもレパートリーとして遊技してもらうには、『機種の価値提案』というプロモーションが課題を解決する一つの重要な要素になります。
おわりに
今回は『市場浸透戦略』と『市場開拓戦略』に関する考え方のコラムでしたが、お店の営業施策で具体的にキャズム越えを目指して、マジョリティ層へ浸透させることが今後の継続課題になります。
これまでの機種やカテゴリーでも市場浸透戦略や市場開拓戦略ができる要素はありますが、その時々で『話題性』が高まっているものやイノベーターやアーリーアダプターの方々の評価が高いものがアプローチとしては有効です。
良いか悪いかという白黒思考ではなく、自店の稼働を上げるためには『何を・どのように伝えて・どのように価値を実感してもらうか』を考えて、仕掛ける内容の浸透確率を上げる取組みです。
マジョリティ層は受動的ではありますが、既存のお客様であれば機種知識は少なからず持っているので、未経験者に対して伝えるよりも労力は減らせます。
もう一つだけ大事なことがあります。
今回お伝えした内容は、「あくまでも全体の中でどれくらいの割合を目指すか」という視点も必要です。
デカへそ機の良し悪しではなく、設置比率をどれくらいにしながら支持してくれるファンを増やしていくかという段階を意識せずに、いきなり「BOX導入してコーナーを作ろう!」としても浸透スピードが追いつきません。
ライトミドルのLT機が徐々に増えているように、段階的に浸透させることも投資面からみても重要な視点となります。
株式会社CFY公式ラインでは
パチンコ業界セミナーや業界時流の情報等、パチンコ経営に役立つ情報を発信しています。
友達登録をぜひ、よろしくお願いします。

リスペクトマインド株式会社 代表取締役 武内 臣介
パチンコ業界に1989年から関わり、日拓では最年少店長で10ヶ月連続店舗表彰や最年少営業職などを歴任し、若手として数々の実績を出し、転職したホール企業では5年間パチンコ50000発、スロット18000枚を1ヶ月も下回らない実績を残す。
2007年の独立後は、ホール企業様の支援を、ホールの専門家として完全応用した『勝つ為のランチェスター戦略』と『差別化価値を作る【コト視点の価値づくり】』で業績向上の結果を出すことと、勝ち抜く社内戦略家育成を継続実施中。
ランチェスター協会の正式なランチェスター戦略インストラクターでもあり、ホール企業支援で業界随一の『勝ち抜くランチェスター戦略』の使い手。
また、パチンコ業界外からの依頼も多く、『コト視点の価値づくり』『火種人材育成』は、魅力的な人材を組織に増やすだけでなく、強力なチームワークの組織にするカリキュラムとして人気が高い。
近年では、業界最大セミナーのJAPaNセミナーに毎年連続登壇し、受講者数上位講師としても活躍している。
2007年の独立後は、ホール企業様の支援を、ホールの専門家として完全応用した『勝つ為のランチェスター戦略』と『差別化価値を作る【コト視点の価値づくり】』で業績向上の結果を出すことと、勝ち抜く社内戦略家育成を継続実施中。
ランチェスター協会の正式なランチェスター戦略インストラクターでもあり、ホール企業支援で業界随一の『勝ち抜くランチェスター戦略』の使い手。
また、パチンコ業界外からの依頼も多く、『コト視点の価値づくり』『火種人材育成』は、魅力的な人材を組織に増やすだけでなく、強力なチームワークの組織にするカリキュラムとして人気が高い。
近年では、業界最大セミナーのJAPaNセミナーに毎年連続登壇し、受講者数上位講師としても活躍している。